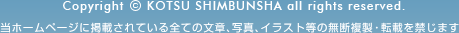北海道の厳しい寒さや雪に対応するため、客室窓を二重構造の窓とし、出入口ドアのレールにヒーターを取り付けるなど、耐寒耐雪構造を強化した車両。このグループでは一番早く誕生した車両で、昭和36年4月から根室本線札幌〜釧路駅間の急行「狩勝」に使用。その後は函館本線函館〜札幌駅間の急行「すずらん」をはじめ、道内各地を結ぶ急行列車として幅広く活躍しました。
昭和44年10月改正で函館〜旭川駅間の特急「北斗」1往復が増発されましたが、車両の落成が間に合わず、昭和45年2月28日までキハ56形7両編成がピンチヒッターとして登場。ヘッドマーク付きの特急列車として運転されたこともありました。
しかし、幹線の特急列車化によって活躍の場が少なくなり、昭和61年3月改正から片側に運転台を増設・改造したキハ53形500番台が誕生。根室本線釧路〜根室駅間の急行「ノサップ」などに使用されましたが、JR化後はキハ27・56形の老朽化が進んだため新型車両へと置き換えられています。
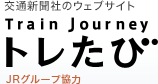
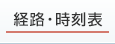
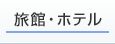








 昭和35年12月、新登場のキハ80系特急形気動車を使用した特急「はつかり」が上野〜青森駅間に登場し、非電化区間においても東海道本線の151系特急電車と同様のサービスが図られるようになりました。これに合わせ、急行形気動車も東海道本線の153系急行形電車と同様の客室設備を備えた車両にすることとなり、キハ28・58系が開発されることが決定。北海道から九州まで幅広いエリアで使用するため、エリアごとの気象条件や線路状況に応じた形式で製造されることになりました。
昭和35年12月、新登場のキハ80系特急形気動車を使用した特急「はつかり」が上野〜青森駅間に登場し、非電化区間においても東海道本線の151系特急電車と同様のサービスが図られるようになりました。これに合わせ、急行形気動車も東海道本線の153系急行形電車と同様の客室設備を備えた車両にすることとなり、キハ28・58系が開発されることが決定。北海道から九州まで幅広いエリアで使用するため、エリアごとの気象条件や線路状況に応じた形式で製造されることになりました。