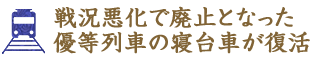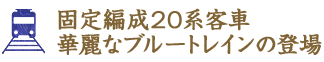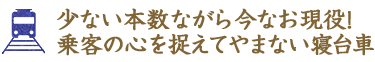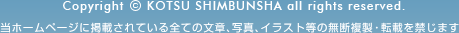長距離列車に連結されていた一・二・三等寝台車は、太平洋戦争の戦況悪化に伴って昭和16年7月に三等寝台車、昭和19年4月には一・二等寝台車の連結を中止しました。戦後は昭和23年12月15日に「特別寝台車」として復活し、昭和24年5月1日には「一等寝台車」の名称に変更。その後は一等寝台車や二等寝台車が続々と復活し、主要幹線の長距離急行列車に連結されるようになりました。
しかし、利用料金が高額な一等寝台車は利用率が低迷していたため、昭和30年7月1日に一等寝台車は廃止となり、その車両はすべて二等寝台車に格下げされました。これにより、2人・4人用区分室の旧一等寝台は二等A寝台、開放式冷房搭載の旧一等寝台は二等B寝台、従来からの二等寝台車は二等C寝台となり、同じ二等寝台でも寝台設備の異なる3タイプが使用されることになりました。
当時の一等車は「イ」、二等車は「ロ」、三等車は「ハ」の記号が使用されていましたが、一等寝台車の廃止に伴って「マイネ」といった一等の形式(マ=車両重量・イ=一等・ネ=寝台車)は「マロネ」となりました。
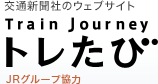
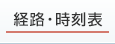
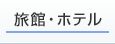


 明治33年(1900)4月8日、私鉄の山陽鉄道(現在の山陽本線)神戸〜三田尻(現在の防府)間の急行列車に一等寝台車が連結されました。これが日本初の寝台車で、車両の長手方向に二段式寝台が並ぶ開放式(通路の両側に二段式8組16名分のベッドを配置)のものでした。同年10月1日には官設鉄道の新橋〜神戸間の急行117・118列車に一等寝台車が連結され、現在の東海道本線および山陽本線で寝台車が活躍。この車両はイギリスとアメリカから各2両の計4両を輸入したもので、各車両には4人部屋が5室設置されていました。当時の一等寝台車の利用料金(新橋〜神戸間は寝台料金4円)は高額なため、一般の庶民にとっては高嶺の花でした。
明治33年(1900)4月8日、私鉄の山陽鉄道(現在の山陽本線)神戸〜三田尻(現在の防府)間の急行列車に一等寝台車が連結されました。これが日本初の寝台車で、車両の長手方向に二段式寝台が並ぶ開放式(通路の両側に二段式8組16名分のベッドを配置)のものでした。同年10月1日には官設鉄道の新橋〜神戸間の急行117・118列車に一等寝台車が連結され、現在の東海道本線および山陽本線で寝台車が活躍。この車両はイギリスとアメリカから各2両の計4両を輸入したもので、各車両には4人部屋が5室設置されていました。当時の一等寝台車の利用料金(新橋〜神戸間は寝台料金4円)は高額なため、一般の庶民にとっては高嶺の花でした。