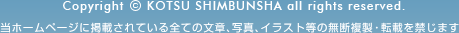昭和43年8月28日の函館本線小樽〜滝川間の交流電化の完成に合わせて登場したのが、日本初の交流専用電車となる711系です。寒冷地を走ることから客室と出入口ドアを仕切るデッキが必要不可欠となり、車体は急行形電車と同様の片開き2扉・ボックスシート配置となっています。昭和44年10月の滝川〜旭川間電化後は、札幌〜旭川間の急行「かむい」や急行「さちかぜ」にも運用。特に昭和46年7月から運転を開始した急行「さちかぜ」は、札幌〜旭川間をノンストップ・1時間36分で結ぶ韋駄天(いだてん)急行として活躍しました。
その後は千歳線・室蘭本線の電化に合わせて711系が増備され、北海道の電化区間のローカル列車や快速列車に活躍。平成4年7月の新千歳空港駅の開業では快速「エアポート」の一部列車にも運用されましたが、その後の721系の増備によりローカル列車を中心に使用されています。なお、2扉では乗降時に時間がかかって遅延の要因となるため、一部車両は3扉化・ロングシート化・デッキの廃止などが実施されました。
北海道用の711系は急行形電車スタイルでしたが、昭和58年7月に九州エリア用として交直流の417系と同様の両開き2扉・セミクロスシートで登場したのが713系です。地方路線の運用に適した2両編成で試作車8両が製造されましたが、国鉄の財政悪化に伴い量産車は製造されませんでした。現在は宮崎空港のアクセス列車を中心に活躍しています。
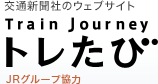
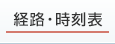
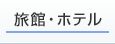
![交流電化区間専用の電車[北海道・九州の交流近郊形電車]交流電化区間専用車両として開発された交流電車。今回は北海道と九州の交流近郊形電車にスポットを当てて紹介します。(文=結解喜幸 写真=結解学)](images/main_title_01.jpg)

 昭和37年に横須賀線用として登場した111系電車の分類において、はじめて「近郊形電車」という表現が使用されるようになりました。大都市近郊の通勤・観光輸送の両面の輸送に適した3扉・セミクロスシート(ボックスシートとロングシートの組み合わせ)で、2扉の急行形電車と4扉の通勤形電車のまさに中間スタイルといえるものです。車両の正面デザインは153系で、側面は通勤用の両開きドアを3カ所に設置し、ドア間および車端にボックスシート、ドア横に2・3人掛けのロングシートを配置するスタイルは、昭和36年に常磐線・鹿児島本線に登場した401・421系交直流電車が元祖になります。
昭和37年に横須賀線用として登場した111系電車の分類において、はじめて「近郊形電車」という表現が使用されるようになりました。大都市近郊の通勤・観光輸送の両面の輸送に適した3扉・セミクロスシート(ボックスシートとロングシートの組み合わせ)で、2扉の急行形電車と4扉の通勤形電車のまさに中間スタイルといえるものです。車両の正面デザインは153系で、側面は通勤用の両開きドアを3カ所に設置し、ドア間および車端にボックスシート、ドア横に2・3人掛けのロングシートを配置するスタイルは、昭和36年に常磐線・鹿児島本線に登場した401・421系交直流電車が元祖になります。