『トレたび』は、交通新聞社が企画・制作・運営する鉄道・旅行情報満載のウェブマガジンです。
![伝統 自然 建築 風土 食|日本人なら行ってみたい あの場所へ|THE定番・極上旅|Vol.14 越後に「日本のミケランジェロ」あり、幕末期の名工・石川雲蝶に見惚れて。[新潟県三条市・長岡市・魚沼市・南魚沼市]](images/header.jpg)













天文3年(1534)開山の曹洞宗の寺院。開山堂には、初代住職の芳室祖春(ほうしつそしゅん)大和尚と、曹洞宗の開祖である道元禅師を中心に、歴代住職が祀られている。 堂内を埋め尽くす『道元禅師猛虎調伏(どうげんぜんじもうこちょうぶく)の図』が有名だが、向拝など外壁に彫られた烏天狗の群像も見事。本堂内陣には襖絵『孔雀遊戯之図』も残されている。
永仁5年(1297)、日印聖人によって創建された法華宗総本山。金物商・内山又蔵に招かれた雲蝶は32歳。本堂欄間や納骨堂、塔頭寺院などに数多くの彫刻を残した。
明治26年(1893)の火事で本堂などは焼失してしまったものの、難を逃れた作品を今も楽しむことができる。
「牛」(写真)や「亀」「猿」といった作品も各塔頭寺院に残されているが、こちらはご住職の不在時などは非公開。
「吉野屋の権現様」として地元の信仰の厚い神社。明治元年(1868)、拝殿が焼失。再建時に、彫刻を依頼されたのが晩年の雲蝶だった。
向拝には龍、拝殿内部には『源頼光四天王の蜘蛛退治』ほか、数々の作品が残る。写真は左から『神功(じんぐう)皇后と武内宿禰(たけのうちのすくね)』『加藤清正と高麗人』。
三条鍛冶の伝統を次世代に伝えるための研修施設。神社仏閣などに使用されている「和釘」づくりや庖丁とぎなどの体験ができるほか、体験イベントも随時開催。
70余年、三条市民に愛され続けるご当地グルメ。カレー味のラーメンだが、店によってカレースープタイプ、カレーのせタイプなどスタイルが違えば、具材も違う。現在、三条飲食店組合カレーラーメン部会ではカレーラーメンが食べられる店を紹介した「食べ歩きマップ」を配布。スタンプラリーも開催している。
上杉謙信が創建した常安寺に、守護神として秋葉神社を勧請。現在の社殿は、天文20年(1551)に建てられたもの。奥の院に施された牛若丸や烏天狗の彫刻は、雲蝶と小林源太郎との共作と伝えられている。
栃尾紬など、養蚕、機織りが大きな地場産業であった栃尾。その基礎を築いた地元の庄屋、植村角左衛門貴渡を「織物業の祖神」として祀った神社。今も「機神様」として親しまれている。社殿には、養蚕から機織りまでの女性の様子や十二支など、雲蝶作品が残る。
「長岡の奥座敷」蓬平温泉。和泉屋では、独特のぬめりがあるその「美肌の湯」を自然と一体化した野趣あふれる風呂で楽しむことができる。「星の湯」(写真)、「月の湯」「風の湯」は、それぞれに趣の異なる露天風呂。貸切露天風呂もある。
日本海の海の幸に加え、地元産コシヒカリはこだわりの釜炊き。長岡野菜、山菜と、ここならではのおいしさが凝縮された料理も評判だ。
平日1泊2食(2名1室)、1名12960円(消費税込、別途入湯税150円)
開基より500余年、曹洞宗の古刹。徳川家康の孫にあたる松平忠直、その子である松平光長の香華所(こうげしょ)として、三葉葵の御紋も許された由緒ある寺。
雲蝶が13年にわたり施した彫刻は天女など仏典に題材をとった色鮮やかなものから、花鳥や山水の水墨画風の彫刻までバリエーションに富んでいる。
和尚が賭けに勝ち、雲蝶を招いたことから「勝縁の寺」としても信仰を集めている。
八海山のふもとに建つ、曹洞宗嶽林寺の末寺。かつては、八海山信仰の修行場として栄えた。本堂の欄間に、麒麟や獏、唐獅子などの雲蝶の作品が残る。 昭和40年に完成したインドグプタ王朝様式の慈雲閣観音堂など、その他の見どころも多い。
上信越の紅葉を360度パノラマ景色で満喫できる八海山ロープウェイ。
この時期、魚沼コシヒカリ発祥の地・南魚沼市ならではのイベント「南魚沼コシヒカリ街道新米キャンペーン」も各地で開催されるので、八海山の美しい紅葉と秋の味覚がダブルで楽しめる。
ロープウェイの夏季営業期間は11月16日まで。
霊峰・八海山の麓、新潟の名水にも指定されている「雷電様の清水」を仕込み水に、越後の地酒の代表格「八海山」を生み出す蔵元。
創業当時の建物を再現した「八蔵」やカフェ、そば店やうどん店が点在する「魚沼の里」や、バーベキューや釣りも楽しめるガーデンパーク、地ビールのブリュワリー、イタリアンレストランなどの複合施設「泉ヴィレッジ」など、南魚沼の美味しいものが集められた施設もある。
信越本線・飯山線を走る、新潟の「酒」をコンセプトにした新しい列車。外観カラーリングは、藍下黒(あいしたぐろ)と呼ばれる青みを帯びた黒と白色が配色され、凛とした「新潟の風土」をイメージしている。
車内には、酒樽をモチーフとしたスタンディングテーブルなどがしつらえられ、厳選された地酒や地元食材にこだわったおつまみを楽しめる。
・詳しくはこちら
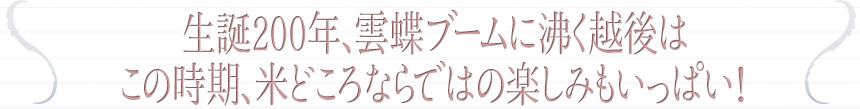
日光東照宮(栃木県日光市)の「眠り猫」、秩父神社(埼玉県秩父市)の「つなぎの龍」など、各地に名作を残した左甚五郎(ひだりじんごろう)。「波を彫らせたら右に出る者なし」と言われた「波の伊八」こと、武志伊八郎信由(たけしいはちろうのぶよし)。江戸期に活躍し、今も名を残す彫刻職人の中でも異彩を放つのが、「日本のミケランジェロ」こと、石川雲蝶(うんちょう)。生誕200年となる今年は、多くの彫刻作品を残した新潟で、雲蝶ブームが起こっています。
私事ながら数年前、魚沼市にある西福寺開山堂で、初めて雲蝶に触れたときの衝撃は忘れられません。堂内を埋め尽くす『道元禅師猛虎調伏の図』、その大きさもさることながら、鮮やかな色彩、構図の大胆さ、虎や龍の今にも飛び出してきそうな迫力。それでいて、人目につかないような裏側にまで細かな仕事が丹念に施されています。東照宮が1日見ていても飽きないということから「日暮門(ひぐらしもん)」と呼ばれるのに対し、1週間見ていても飽きないのでは……と思わせる仕事ぶりが、そこには生々しく残されていました。「仕事嫌い」と伝えられている雲蝶ですが、これほどの仕事をする人です。一度仕事に入れば、命を削って打ち込んでしまう。それがわかっているだけに、生半可な気持ちでは鑿(のみ)を握れなかったのはないか、と思いました。
石川雲蝶、本名は安兵衛。江戸時代末期である文化11年(1814)、江戸・雑司が谷に生まれ、明治16年(1883)、新潟・三条でこの世を去りました。
江戸で石川流の彫刻師として活躍していた雲蝶に惚れ込んだのが、三条の金物商・内山又蔵。檀家総代を務めていた三条の本成寺(ほんじょうじ)の彫刻を依頼します。そのとき、雲蝶を説得した言葉が「終生、良い鑿(のみ)と良い酒を与える」。真偽のほどはわかりませんが、三条鍛冶が生み出す刃物の素晴らしさ、越後の酒の旨さ、そして職人であり、無類の酒飲みでもあった雲蝶を結びつけるエピソードとして、これほどのものはないでしょう。
それでは、雲蝶とゆかりの深い三条市から、旅を始めることにいたしましょう。越後移住のきっかけとなった本成寺には、彫刻作品の他、雲蝶の墓も残ります。同じく三条市にある石動(いするぎ)神社では、人間の本質にまでたどり着いたような、晩年の雲蝶の作品が待っています。
三条鍛冶道場では、雲蝶の時代から変わらぬ伝統を見るだけでなく、体験することも。さらにおもしろいのが、市が総力を挙げて取り組んでいる「三条カレーラーメン」の存在。市民に愛され続けて70余年。「B級グルメ界のスター候補」との呼び声も高い、この名物をぜひとも先物買いしておきたいものです。
そして、お隣の長岡市栃尾にも、見逃せない作品が。上杉謙信ゆかりの秋葉三尺坊大権現では、牛若丸や烏天狗がドラマティックに、貴渡(たかのり)神社では、養蚕から機織りにたずさわる女性たちの様子がいきいきと描かれています。
雲蝶旅の宿泊は、長岡の奥座敷、蓬平温泉の和泉屋にて。美肌の湯として名高い温泉とともに楽しみなのが、2011年から県内の旅館の若旦那たちの発案で始まった「にいがた朝ごはんプロジェクト」。日本一のコシヒカリをその土地の水で最高においしく炊き上げ、その土地ならではのおかずでいただく究極の朝ごはんです。この秋も、県内20地域の旅館が参加。そのラインナップの充実ぶりは驚くほど。
そんな朝ごはんからスタートする2日目は一路、魚沼市へ。めぐるのは、冒頭で紹介した西福寺開山堂に永林寺。永林寺にも、雲蝶のおもしろいエピソードが残されています。
三条の本成寺の彫刻を見た永林寺の弁成(べんせい)和尚が、博打で借金を抱えていた雲蝶に「あなたが勝てば借金の支払いを引き受けるが、私が勝ったら本堂に彫刻を彫る」という賭けを持ちかけた、というもの。この賭けに負けた雲蝶は13年間をかけ、100点を超す作品を永林寺に残しました。永林寺、西福寺開山堂ともに、雲蝶40代の、まさに絶頂期の作品といえるでしょう。
旅の最後に立ち寄るのは、南魚沼市。この地にも、雲蝶が好んで彫ったという唐獅子や牡丹が残される龍谷寺があります。
南魚沼市といえば、魚沼コシヒカリ発祥の地。新米のこの時期、「南魚沼コシヒカリ街道新米キャンペーン」と銘打って、日本一のコシヒカリの新米を堪能できるイベントが各所で開催されています。
お土産には、越後の地酒の代表格「八海山」を購入。自宅でゆるりと味わいつつ、旅の余韻を楽しみたいもの。その際は、酒好きだった雲蝶への献杯もどうぞお忘れなく……。



文= 秦 まゆな(はた・まゆな)
PROFILE
日本文化案内人・文筆家。歴史と伝統文化に裏打ちされた、真の日本の楽しみ方を提唱すべく、日本全国を駆け回り中。その土地ならではの食、酒、温泉、祭りが大好物。
著書『日本の神話と神様手帖 あなたにつながる八百萬の神々』(マイナビ)。
フェイスブックも更新中!