『トレたび』は、交通新聞社が企画・制作・運営する鉄道・旅行情報満載のウェブマガジンです。
![伝統 自然 建築 風土 食|日本人なら行ってみたい あの場所へ|THE定番・極上旅|Vol.15 戦乱の世を戦い抜いた真田一族の足跡をたどる。冬の信州・上田の旅[長野県上田市]](images/header.jpg)














真田昌幸によって築城され、2度の上田合戦の舞台となった上田城。現在は、桜の名所として多くの人に愛されている。復元された櫓門内部など見学可(大人250円、冬季は不可)。
信繁の祖父・幸隆の代、真田の郷を本拠地としていたときの城跡。広大な規模の郭を誇り、一帯を見下ろす眺望もすばらしい。戦乱の世には戦いのための眺望も、平和な現代では絶好のビューポイントに。
関ケ原の戦いの後、上田城が取り壊されたため、跡をついだ真田信之が構えた居館。上田藩主が仙石氏、松平氏と変わっても、藩主邸はそのまま使われていた。現在は、上田高等学校。
寛文5年(1665)創業。信州の米と水と自然にこだわり、代表銘柄「信州亀齢(きれい)」をはじめとする、きれいな日本酒を醸す。
柳町には、岡崎酒造をはじめ、昔ながらの日本家屋を利用した味噌屋、蕎麦屋をはじめ、スペイン料理屋に天然酵母のパン屋など、個性豊かな店が並ぶ。
北向(きたむき)観音に隣接する宿。部屋付の露天風呂から北向観音が見える客室もあり、贅沢な時間を満喫できる。大浴場・悠々の湯は総檜で作られ、木の香と高い吹き抜けの天井が心地よい。貸切温泉も石づくりの広い露天風呂付。平日1泊2食(2名1室)、1名25000円~(税別)
天然の岩間をそのまま浴槽にし、野飼いの牛が傷を癒したことから「牛湯」と呼ばれていた時代もある。真田氏の隠し湯としても知られ、池波正太郎の『真田太平記』にも、この湯がしばしば登場する。建物の前には、池波正太郎の筆による「真田幸村公隠しの湯」の石碑が立つ。
平安時代初期、慈覚大師円仁により開創。本堂は南向きに建てるのが常の日本において、北向きなのは珍しい。御本尊は千手観音、現世利益を願う場所とされる。
一方、善光寺は南向き。阿弥陀如来を御本尊に未来往生を願う場所とされ、現世と未来の両方を願え、向き合っていることから、どちらか一方だと「片詣り」といわれるようになった。
鎌倉の建長寺などと並んで、日本では最も古い臨済禅宗寺院のひとつ。天正16年(1588)頃、曹洞宗に改められた。木造八角三重塔は、全国でここにしかない貴重な建築として国宝に指定。その後の研究で鎌倉時代末期の建立ということが判明した。
万物に生命力をあたえる「生島大神」と万物に満足を与える「足島大神」を御祭神とする信州屈指の古社。この二柱の大神に、建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)が米粥を煮て奉じたという故事は、今も神事として残る。
長野県上田市にあるローカル線「別所線」。長野新幹線、しなの鉄道が乗り入れる上田駅から別所温泉駅まで全15駅、11.6kmを結ぶ。
写真は、風景画家として知られる原田泰治氏のイラストをラッピングした車両「自然と友だち2号」。昆虫や植物、動物などのシンボルが描かれ、信州・上田の自然と共存して走る別所線への思いが込められている。
・詳しくはこちら
2014年夏より走り出した、しなの鉄道の観光列車「ろくもん」。車両はJR九州の車両などを手がける水戸岡鋭治氏のデザイン。地元ゆかりの戦国武将・真田氏の意匠「ろくもん」マークが随所に施されている。
写真は、旅行商品「食事付きプラン」の和懐石。厳選された信州の食材と冬景色をゆっくりと楽しめる。土・休日・冬(夏)休みを中心に、軽井沢~長野間で運転。
・詳しくはこちら
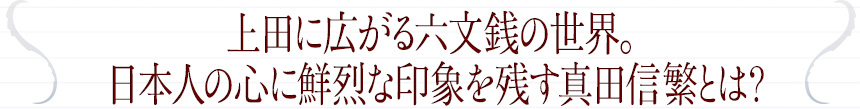
NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』がこのほど最終回を迎えましたが、すでに発表されている平成28年の大河ドラマは、三谷幸喜作『真田丸』。主人公は、真田信繁。真田幸村といったほうが、通りがいいかもしれません。けれども、その名が使われ出したのは、彼の死後、物語の中でのこと。生前、「幸村」と記している書状などはなく、本人が「幸村」を名乗ったかどうかは定かでないとされています。今回は、そんな真田信繁ゆかりの地、長野県上田市へと参りましょう。
JR東京駅から長野新幹線「あさま」で約1時間半。上田駅に降り立つと、そこはすでに六文銭の世界。目につくものすべて、それこそ駅にあるゴミ箱にも、真田家の家紋である六文銭が記されています。駅前の真田幸村(信繁)像をカメラに収め、まずは真田氏の居城であった上田城をめざします。
天正11年(1583)、信繁の父、昌幸が築城した上田城は、2度にわたる徳川の大軍勢との戦いの舞台となった城。本丸東虎口櫓門が平成6年に復元されたほか、本丸には3つの櫓や歴代城主を祀った真田神社、抜け道として使ったとされる真田井戸なども残されています。徳川秀忠率いる3万8000人からなる大軍勢をわずか2500人で迎え撃ち、敗走させた真田軍。昌幸の戦上手とこの上田城の堅牢さを伝える史実です。
上田城から北東に7kmほど行ったところには、「真田氏発祥の郷」が。信繁の祖父にあたる幸隆がこの地の領主となり、初めて真田を名乗ったともいわれています。上田城を築城する前の居館だった場所が「御屋敷公園」として整備されているほか、真田氏本城跡や真田氏のかつての菩提寺である長谷寺、真田郷の産土神が祀られる山家神社など、真田にまつわる見どころが満載です。
幸隆の時代から、甲斐国の武田氏の家臣として頭角を現してきた真田氏は、続く乱世に否応なく巻き込まれていきました。関ケ原の戦いで父である昌幸は、長男・信之は徳川方、自分と信繁は豊臣方として戦う苦渋の決断を下します。ご存知の通り、結果は徳川の圧勝となり、昌幸・信繁親子は高野山へ配流となりました。
昌幸・信繁親子が蟄居(ちっきょ)した屋敷跡「真田庵」は、今も高野山の麓(和歌山県伊都郡九度山町)に残されています。人里離れた場所の「屋敷」とも呼べないような簡素な造りですが、門に六文銭が彫られていることに真田の矜持(きょうじ)が感じられます。ここで父、昌幸を見送り、14年もの蟄居生活を送った信繁。真田庵の地に立ったとき、出陣を請われた大坂冬の陣、夏の陣で鬼神のような活躍を見せたその境地がわかるような気がしました。
一方、徳川方についた兄・信之は関ケ原の合戦後、上田藩主となりました。現在の上田高等学校は、信之が建てた居館跡でもあり、壕や土塁などに当時の面影が残っています。上田には、越後と江戸を結ぶ北国街道が走ることも、この地が活気づいた大きな要因でした。往時の姿をとどめた柳町には、創業350年を迎える岡崎酒造はじめ、立派な卯建(うだつ)のある家屋が並び、今もにぎわいを見せています。
そろそろ今宵の宿、別所温泉に向かいましょう。上田電鉄別所線に乗れば30分ほどで、昭和初期建築のレトロな駅舎、別所温泉駅に到着します。別所温泉の起源は古く、日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の折に発見されたという説、清少納言の『枕草子』に記されている三名湯のひとつ「七久里(ななくり)の湯」ではないかという説など、諸説あります。
「かしわや本店」はじめ、良質な湯が楽しめる温泉宿のほか、木曽義仲ゆかりの「大湯」、慈覚大師円仁ゆかりの「大師湯」、真田氏ゆかりの「石湯」など、趣ある共同浴場が3つもあるのもうれしい限り。長野市の善光寺と対で参拝するとよいとされる北向観音、国宝・八角三重塔のある安楽寺など見ごたえのある名刹もあり、ゆるりと連泊したい誘惑にかられます。
帰りは、別所線を途中下車して、生島足島(いくしまたるしま)神社へ。真田氏はもちろん、武田信玄の願文なども残る古社です。7年に一度の御柱祭で有名な諏訪大社に「諏訪大神」として祀られる建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)という神様がいます。真田の時代よりも遥か昔の神話時代、出雲の国譲りに敗れた建御名方富命が諏訪の地にお鎮まりになる前、この地へやってきて、生島大神、足島大神に奉仕したと伝えられています。神池に囲まれた神島に建つ御本殿を眺めていると、この地に息づく、もうひとつのドラマに魅了されてしまうこと、間違いなしです。



文= 秦 まゆな(はた・まゆな)
PROFILE
日本文化案内人・文筆家。歴史と伝統文化に裏打ちされた、真の日本の楽しみ方を提唱すべく、日本全国を駆け回り中。その土地ならではの食、酒、温泉、祭りが大好物。
著書『日本の神話と神様手帖 あなたにつながる八百萬の神々』(マイナビ)。
フェイスブックも更新中!