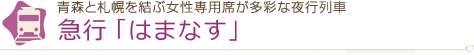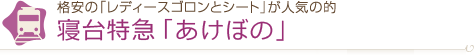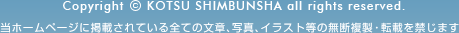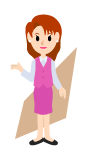 東京の通勤・通学の足として電車が活躍するようになっていた明治45年(1912)1月、中央線中野駅と昌平橋駅(現在の御茶ノ水駅と神田駅の間にあった)の間で朝夕2回の「婦人専用車」が運行されました。これが「レディースカー」(女性専用車)のはじまりです。残念ながら短期間で運行は終了しましたが、35年後の昭和22年5月に「婦人子供専用車」として中央線で復活。終戦後の混乱期の混雑率は300%を超える区間もあり、女性や子供が通勤・通学時に電車を利用するのは大変であっただけに好評を博しました。
東京の通勤・通学の足として電車が活躍するようになっていた明治45年(1912)1月、中央線中野駅と昌平橋駅(現在の御茶ノ水駅と神田駅の間にあった)の間で朝夕2回の「婦人専用車」が運行されました。これが「レディースカー」(女性専用車)のはじまりです。残念ながら短期間で運行は終了しましたが、35年後の昭和22年5月に「婦人子供専用車」として中央線で復活。終戦後の混乱期の混雑率は300%を超える区間もあり、女性や子供が通勤・通学時に電車を利用するのは大変であっただけに好評を博しました。
昭和24年9月には京浜東北線でも運転されるようになりましたが、さらに昭和32年6月には老人や子供が優先的に利用できる「老幼優先車」も登場。しかし、通勤時間帯に老人の利用は少ないため、短期間で姿を消してしまいました。
混雑の激しい中央線における「婦人子供専用車」は昭和48年9月まで運行されていましたが、同年9月15日の敬老の日から登場した「シルバーシート」(車両の一部に優先席を設置)に役目を譲りました。
その後、電車内における痴漢被害を訴える女性が多いことから、平成12年12月に京王電鉄が「女性専用車両」(週末の深夜に新宿を発車する一部の車両を専用車とした)を試験的に設定。これが好評を博したことから翌年3月には23時以降に新宿を発車する優等列車に「女性専用車両」が導入されました。さらに京阪や阪急も本格導入したのに続き、関東や関西の大手私鉄にも「女性専用車両」が誕生。JRでは埼京線や関西エリアの東海道線・大阪環状線・片町線・東西線・福知山線・阪和線・和歌山線などで運行されています。

- 女学校前に到着した女性専用東京市電

- 中央線の「婦人子供専用車」のプレート

- 埼京線の「女性専用車」と乗車口窓内
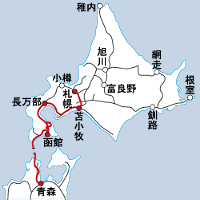
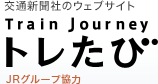
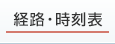
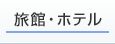
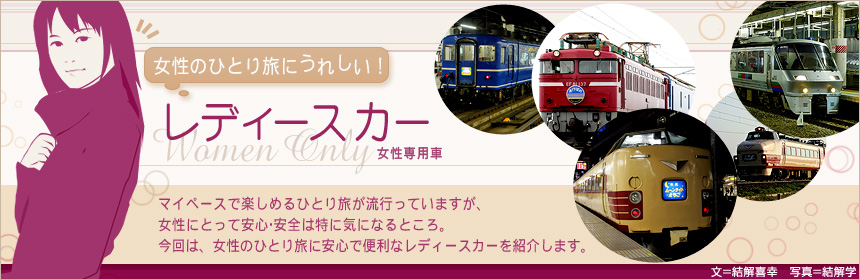






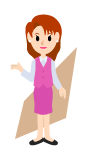 東京の通勤・通学の足として電車が活躍するようになっていた明治45年(1912)1月、中央線中野駅と昌平橋駅(現在の御茶ノ水駅と神田駅の間にあった)の間で朝夕2回の「婦人専用車」が運行されました。これが「レディースカー」(女性専用車)のはじまりです。残念ながら短期間で運行は終了しましたが、35年後の昭和22年5月に「婦人子供専用車」として中央線で復活。終戦後の混乱期の混雑率は300%を超える区間もあり、女性や子供が通勤・通学時に電車を利用するのは大変であっただけに好評を博しました。
東京の通勤・通学の足として電車が活躍するようになっていた明治45年(1912)1月、中央線中野駅と昌平橋駅(現在の御茶ノ水駅と神田駅の間にあった)の間で朝夕2回の「婦人専用車」が運行されました。これが「レディースカー」(女性専用車)のはじまりです。残念ながら短期間で運行は終了しましたが、35年後の昭和22年5月に「婦人子供専用車」として中央線で復活。終戦後の混乱期の混雑率は300%を超える区間もあり、女性や子供が通勤・通学時に電車を利用するのは大変であっただけに好評を博しました。