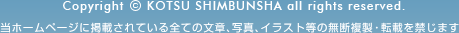日本海縦貫線大阪〜青森間の電化工事が進捗すると、直流〜交流60Hz〜直流〜交流50Hzと3電源方式の電化区間を直通できる電気機関車が必要不可欠なものとなりました。そこで、当時の直流電気機関車の標準タイプとして活躍していたEF65形をベースとした交直流電気機関車が開発されることになり、昭和43年に3電源対応のEF81形1号機が誕生しました。外観スタイルはEF65形と同じですが、塗色はEF80形と同様に交直流車両の標準色である「赤13号(ローズピンク)」で、交直流電気機関車であることは一目でわかるようになっています。
EF81形は昭和44年までの2年間に38両が製造され、まずは北陸本線金沢〜新潟操車場間の貨物列車の牽引機として活躍。さらに昭和47年から昭和52年にかけて39号機から136号機が増備され、東海道本線〜湖西線〜北陸本線〜信越本線〜羽越本線を経由する大阪〜秋田間の寝台特急「日本海」や急行「きたぐに」、普通列車、貨物列車の牽引を担当するようになりました。また、東北本線では隅田川〜福島間の貨物列車の牽引に使用され、常磐線のEF80形とともに、首都圏エリアにローズピンクの車体を輝かせていました。
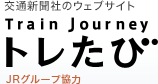
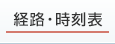
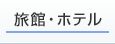
![旅客・貨物用の万能機[EF81形 交直流電気機関車]直流&交流電化区間を直通運転できる交直流電気機関車。今回はブルトレから貨物列車まで幅広く活躍するEF81形にスポットを当てて紹介します。(文=結解喜幸 写真=結解学)](images/main_title_01.jpg)

 日本の鉄道の電化方式は昭和30年代前半まで直流でしたが、当時の欧州では送電ロスが少なく、コストパフォーマンスに優れた交流電化方式の実用化が進められていました。日本では昭和30年から仙山線において交流電化試験が実施され、その結果を踏まえて日本でも商業用の交流電源を使用した電化の実用化の目処が立ちました。昭和32年10月、北陸本線田村〜敦賀間の交流電化が完成し、さらに常磐線取手〜勝田間や鹿児島本線門司港〜久留米間の交流電化が推進されました。
日本の鉄道の電化方式は昭和30年代前半まで直流でしたが、当時の欧州では送電ロスが少なく、コストパフォーマンスに優れた交流電化方式の実用化が進められていました。日本では昭和30年から仙山線において交流電化試験が実施され、その結果を踏まえて日本でも商業用の交流電源を使用した電化の実用化の目処が立ちました。昭和32年10月、北陸本線田村〜敦賀間の交流電化が完成し、さらに常磐線取手〜勝田間や鹿児島本線門司港〜久留米間の交流電化が推進されました。